定期講座用に使ってきた室内用の「パーラー・パイプ」ですが、
皆さんが自分専用の“My Pipe”を持つようになられたので必要なくなりました。
このパーラー・パイプですが、パキスタン製の安物に少し手を加えて騙しだまし使ってきたものです。
あくまでもハイランドバグパイプへの繋ぎ役だし、しっかりとしたものは殆ど存在していなく、
有ってもとても高価だったからです。
パキスタン製の「Rose Wood」と称される材質ですが、それは名ばかりで本来の高級材とはかけ離れた粗悪な材質です。しかも「白太:しらた」と呼ばれる肉で言うならば脂身の部分が多用され、柔らかくバサバサで悲しくなるほどのチープさです。水分にも弱く、とても褒められた材質ではありません。おまけに下地仕上げもしないままただニスを塗りたくっただけで、そのニスでさえ割と簡単に剥がれてしまいます。
なので、前々からずっと気になっていたこのパイプらに化粧直しをしてみようと思いました。
パキ製でよくある「Black Rose Wood」のように、隠ぺい力の強い黒い塗料で力任せに覆ってしまう事だけは避けようと思いました。
以下、計画の段取りです。
1.プロジェクティング・マウントとフェラルの取り外し
2.元の塗料の剥離
3.剥離剤除去→サンドペーパーで表面を滑らかに(♯600~2000)
4.真鍮ブラシでブラッシング
※この段階で砥の粉で目地を埋めても良いのですが、砥の粉の色が刷り込まれる恐れがあるで省略
5.乾布摩擦による艶だし
6.ブラックウッド風になるように表面への染めこみ(様子見ながら調整)
7.表面を軽~く研磨→艶出し
8.超薄のニスで塗膜(数回)
9.軽くブラッシング
10.乾布摩擦による艶だし
Koiwai流だとざっとこんな感じです。
「そんなやり方ではダメだ!」とご指摘がありそうですが、そこのところはご勘弁ください。(笑)
一番悩ませたのが6の「ブラックウッド風になるように表面への染めこみ」です。
当初オイルステインのみで行けるかと思いましたが、そう簡単には〝ブラックウッド〟にはなりません。
墨汁・水性アクリルの黒は水分が多いのでバサバサになってしまい、せっかくの表面処理が台無しです。
いろいろ試行錯誤したあげく大丈夫かなって思ったのは、「ぺんてる 筆ペン」でした。
一応水性ですが木部に負担掛けずに染み込んでいきます。
乾いたところでメリヤス布で磨けば透明感もあります。
そのうえで油性のオイルステイン(こげ茶系)を刷り込みました。
途中小さな紆余曲折もありましたが、だいたい思ったとおりに仕上がりました。
コンセプトは「いかにしてニス仕上げをしていないブラックウッド風にみせるか」「透明感」「ブラックウッドのような自然なムラ」なので、極力ニスのテカテカ感は控え半艶仕上げにしてあります。
色の明るい部分は元のままで、最終的には見えなくなります。
まだ木自身が構えているので落ち着いていませんが、時間とともにしっくりする事でしょう。
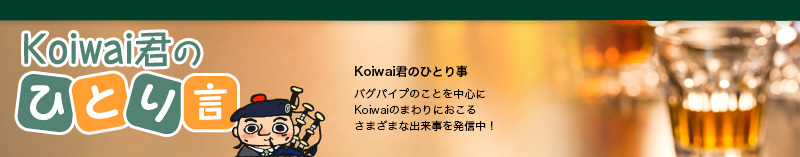






Koiwai先生の楽器加工技術編を、いつも興味深く拝見しています。
今回は定期講座で練習させていただいていたあのパーラーパイプが、何とも渋いパイプに生まれ変わりましたね!びっくりです。
木とか皮とかの素材は環境の変化を受けやすいので手はかかりますが、反面、さまざまに変化させることもできるので素敵ですね。
いつか実物を見せてくださいませ。
mimozaさん
コメントありがとうございます。
そうです。あのパーラーです。(笑)
ポリッシュ専用マシンがあれば造作もないのですが、あいにく指だけなので完璧には程遠いです。(涙)
今は追加として、亜麻仁油による「オイル」仕上げをちまちまやっています。指で薄~くオイルをのばし、乾いたら手でひたすら擦るのみです。これを何度も繰り返します。時間がとってもかかる贅沢な仕上げ方ですが、ニスにはない上品な艶が出せます。筆ぺんで染める前に、部分的に紫系を染みこませておいても良かったと思います。
木や皮ってホント好きなんですよ~!
そのうち講座に持って行きますね。